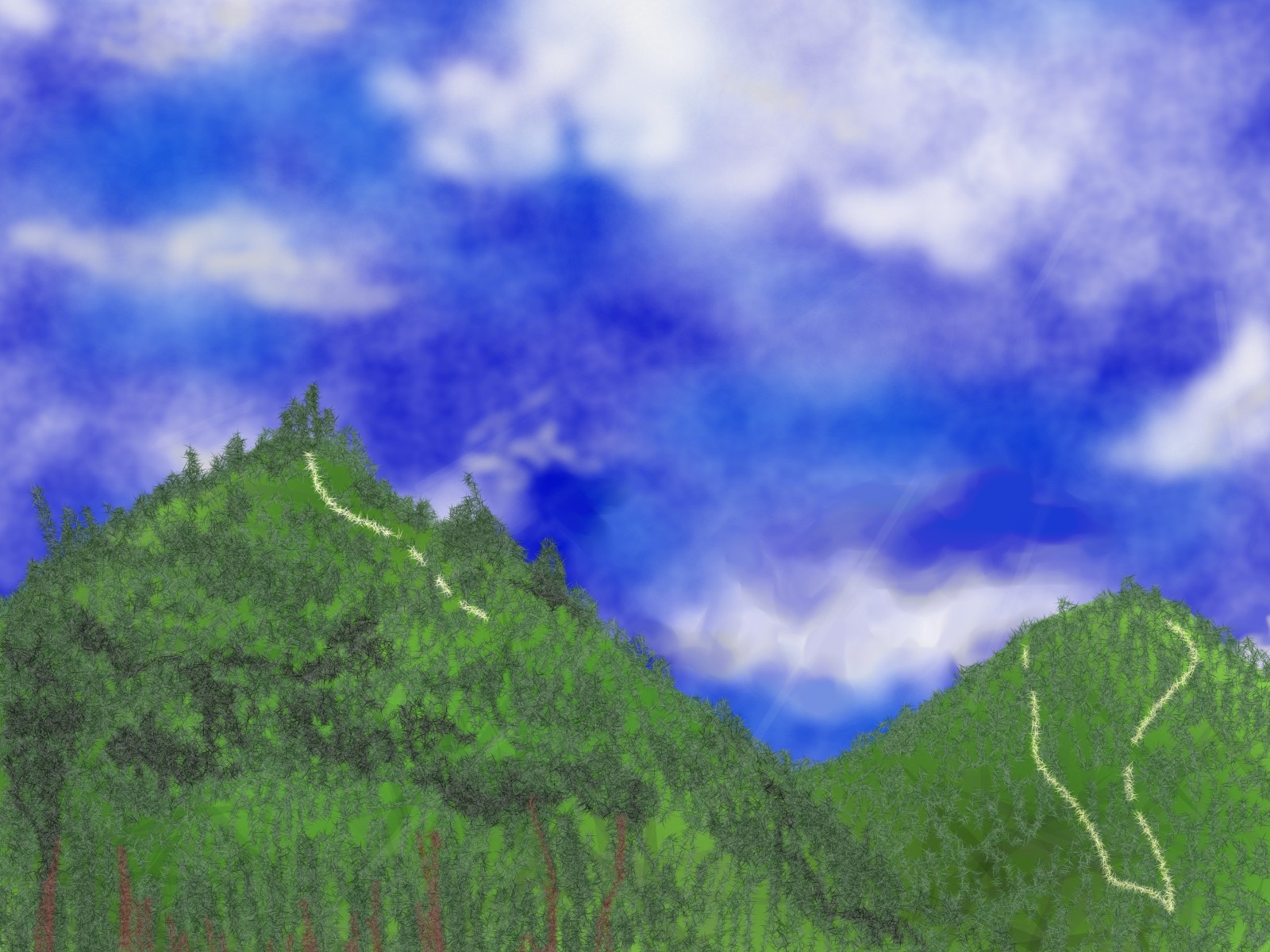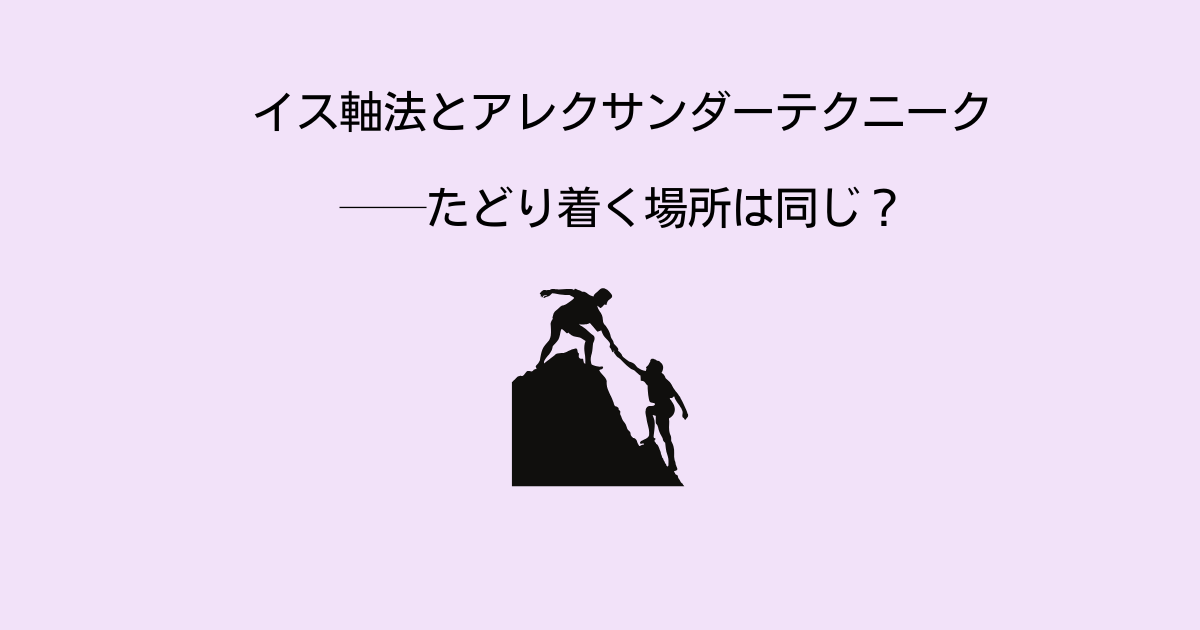今日は、イス軸法とアレクサンダーテクニークの「行き着く地点」について、少し書いてみたいと思います。
イス軸法を知って、もうすぐ2年。ようやくその輪郭が見えてきました。
まず驚いたのは、イス軸法とアレクサンダーテクニークの導入のアプローチが真逆であるということです。
アレクサンダーテクニークでは「頭・首・背中の関係を考えましょう」といいます。
一方、椅子軸法では「背中は考えてはいけない」といいます。
これは、特にアレクサンダーテクニークを先に学んだ人にとっては戸惑うポイントかもしれません。実際、私も最初はとても混乱しました。「いったい、どちらが正しいの?」と。でも、だからこそ私はイス軸法を深く学びたいと思ったのかもしれません。
そして最近ようやくわかってきたのは──どちらも正解だということです。
たとえば山に登る時、Aコースを通るのか、Bコースを通るのか。その違いのようなものだと感じています。
アレクサンダーテクニークでは、自分に方向性を与える「ダイレクション」という言葉を使い、「首が自由で」「背中が広がって」などと自分に言い聞かせるプロセスがあります。
ただし、それを間違ったやり方で行うと、かえって自分を固めてしまうこともあるのです。
その“間違い”を避けるために、イス軸法では最初から「体の部位を考えない」ことが強調されます。
でも、アレクサンダーテクニークでは「もしかたまってしまっても、そこに気づき、工夫すること自体が大切」と考えます。
そしてイス軸法においても、最終的には「背中を考えても、何をしても、軸が抜けない体」にたどり着くのだということが、最近ようやく実感としてわかってきました。
まとめると──
アレクサンダーテクニークもイス軸法も、目指すところは同じ。ただ、スタート地点が違うだけ。そんなふうに感じています。
アレクサンダーテクニークは頭と首の関係から、イス軸法は骨盤からのアプローチ。
どちらもとても大切な視点です。そして、両方を学べばきっと最強ですね👍